ã€€æ—¥æœ¬æ˜ ç”»å°‚é–€ãƒãƒ£ãƒ³ãƒãƒ«ã§ã€æ¨‹å£çœŸå—£ãŒæ±å®ç‰¹æ’®æ˜ 画を語る特番をやã£ã¦ã¦ã€ã€Žãƒžã‚¿ãƒ³ã‚´ã€ã®æš—é»’é¢ã©ã‚ã©ã‚ã®ç™»å ´äººç‰©ãŸã¡ã¯å½“時ã€å…本木ã§æ´¾æ‰‹ã«éŠã‚“ã§ãŸã‚°ãƒ«ãƒ¼ãƒ—ãŒæ°—ã«å…¥ã‚‰ãªãã¦ãã®ã¾ã‚“ã¾ãƒ¢ãƒ‡ãƒ«ã¨ã—ã¦ä½¿ã£ã¦ã‚„ã£ãŸã¨æœ¬å¤šçŒªå››éƒŽç›£ç£ã‹ã‚‰ç›´æŽ¥è´ã„ãŸã¨ã‹ã„ã†è©±ã‚’ã—ã¦ãŸã€‚
 ワイルド派ã§ã¡ã‚‡ã£ã¨ç—…çš„ãªä½œå®¶ãŒå¤§è–®æ˜¥å½¦ã€ã„ã‹ã«ã‚‚良è˜æ´¾ã®ã‚ˆã†ã§çµå±€ã²ã¨ã‚Šã ã‘逃ã’出ã—ã¦ã—ã¾ã†ãƒ¨ãƒƒãƒˆãƒžãƒ³ãŒå €æ±Ÿè¬™ä¸€ã€ãã—ã¦ã€é‡‘ã®åŠ›ãŒãªããªã‚‹ã¨ãªã‚“ã«ã‚‚ã§ããªããªã‚‹ä¸€ç•ªæƒ…ã‘ãªã„土屋嘉男ã®é’年実æ¥å®¶ãŒè¥¿æ¦ã®å ¤ç¾©æ˜Žãªã‚“ã ã¨ã€‚
 å¥å…¨è·¯ç·šã®æœ¬å¤šçŒªå››éƒŽã«ã‚ã‚“ãªæš—é»’å‚‘ä½œæ˜ ç”»ã‚’æ’®ã‚‰ã›ã‚‹ã¾ã§ã®å·¨å¤§ãªã‚‹è² エãƒãƒ«ã‚®ãƒ¼ã‚’注ãŽè¾¼ã‚“ã ã®ãŒå ¤ç¾©æ˜Žã ã£ãŸã¨ã¯ã€å›½åœŸã‚’è’廃ã•ã›ãŸå ¤ä¸€æ—唯一最大ã®åŠŸç¸¾ã ãªã€‚金ã®åŠ›ã‚’ãƒãƒƒã‚¯ã¨ã—ãŸå ¤ç¾©æ˜Žã®é¼»æŒã¡ãªã‚‰ãªã•ã«ã¯ã€ã€Žã‚´ã‚¸ãƒ©ã€ã‚’産ã¿å‡ºã™ã ã‘ã®ã‚¨ãƒãƒ«ã‚®ãƒ¼ã‚’監ç£ã«ä¸ŽãˆãŸæˆ¦ç«ã«ã‚ˆã‚‹å›½åœŸã®è’廃ã¨ãƒ“ã‚ニã®æ°´çˆ†ã«åŒ¹æ•µã™ã‚‹å¨åŠ›ãŒã‚ã£ãŸã‚ã‘ã 。
 ã“ã‚“ãªæ™‚å±€ãƒã‚¿ã¨ãƒ²ã‚¿ã‚¯è©±ãŒäº¤å·®ã™ã‚‹é¢ç™½ã’ãªè©±ãŒã‚¦ã‚§ãƒ–上ã§ã¾ã£ãŸã出ã¦ãã¦ãªã„ã®ã¯ã©ã†ã„ã†ã“ã¨ã‚ˆã€‚
 ã“ã‚Œã»ã©ãŠã„ã—ã„話ãŒæ²™éšå·ç„¡è…¸å¥³å²ã®ãƒšãƒ¼ã‚¸ã«ã•ãˆãªã„ã‚„ã‚“ã‹ã€‚
 ã¾ã£ãŸãã€ã‚¦ã‚§ãƒ–ã®é¢ã€…ã¯åŒã˜ã‚ˆã†ãªãã らãªã„話をãã‚‹ãã‚‹å»»ã—ã¦ã„ã‚‹ã ã‘ã§ã€ã“ã†ã„ã†è‚è…Žãªã“ã¨ã¯å–ã‚Šæƒãˆã¦ãŠã‚‰ã‚“ãªã€‚ãã‚Œã§ã„ã¦ã€ã‚‚ã†ãªã‚“ã ã‹ã‚¦ã‚§ãƒ–ã¯æˆç†Ÿã—切ã£ãŸã‹ã®ã‚ˆã†ãªé”観ã—ãŸã‚ˆã†ãªã“ã¨ã‚’云ã£ãŸã‚Šã‚‚ã™ã‚‹ã‹ã‚‰ã‚¿ãƒãŒæ‚ªã„。
 ã‚ã®æ¯’ã‚ノコã¯ã¨ã‹ã€å¤©æœ¬è‹±ä¸–ãŒã‚„ã£ã¦ãŸã‚ã®æ€ªç‰©ã¯ã¨ã‹ã„ãらã§ã‚‚膨らã¾ã›ã‚ˆã†ã¯ã‚ã‚‹ã ã‚ã†ã«ã€‚撮影ã«ä½¿ã£ãŸã‚ノコã¯é¤…ã«é£Ÿç´…å¡—ã£ãŸã‚‚ã®ã§ãšã„ã¶ã‚“ã¨ã†ã¾ã‹ã£ãŸã‚‰ã—ã„ã‘ã©ã€ã¨ãã«åœŸå±‹å˜‰ç”·ã¯ç‰¹åˆ¥ã®æ³¨æ–‡ã‚’出ã—ã¦ç ‚ç³–ã‚’ã¾ã¶ã—ã¦ãŸã‚‰ã—ã„ã—。
 ã»ã‚“ã¨ã«å”¯ä¸€ã€3å¹´å‰ã®2ã¡ã‚ƒã‚“ãã‚‹ã®æ›¸ãè¾¼ã¿ã«ã²ã¨ã¤ã‚ã‚‹ã ã‘。ã“ã“ã§ã¯ä½œå®¶ãŒçŸ³åŽŸæ…Žå¤ªéƒŽã¨ã„ã†ã“ã¨ã«ãªã£ã¦ã‚‹ã‘ã©ã€ã©ã¡ã‚‰ã‚‚æ¨ã¦ãŒãŸã„ãªã€‚
 『マタンゴã€ã¯1963å¹´ã®å°åˆ‡ã‚Šã§ã€åˆ¶ä½œã—ã¦ã„ãŸå‰å¹´ã¯ã¡ã‚‡ã†ã©å ¤ç¾©æ˜ŽãŒè‹—å ´ã‚¹ã‚ãƒ¼å ´ã¨è‹—å ´ãƒ—ãƒªãƒ³ã‚¹ãƒ›ãƒ†ãƒ«ã§ä¸€ç™ºå½“ã¦ãŸ28æ³ã®é ƒã‹ã€‚
 ã¾ã å…本木野ç£ä¼šã¨ã‹ã‚ã£ãŸæ™‚代ã ã‘ã©ã€ã©ã‚“ãªé¢åã¨ã¤ã‚‹ã‚“ã§ã„ãŸã®ã‹ã€æ°´é‡Žä¹…美ã®ãƒ¢ãƒ‡ãƒ«ãŒèª°ãªã®ã‹ã€èª°ã‹ãã£ã¡ã‚Šè£ã‚’å–ã£ã¦ã‚¦ã‚§ãƒ–ã«ä¸Šã’ã¨ã„ã¦ã‚ˆã€‚よã‚ã—ãé ¼ã¿ã¾ã™ã€‚
 ã‚ャライメージ的ã«ã¯ç¾©æ˜Žã‚ˆã‚Šã‚‚清二ã®ã»ã†ãŒã¯ã¾ã‚‹ã¨ã“ã‚ã‚‚ã‚ã‚‹ã®ã§ã€æœ¬å¤šç›£ç£ã‹æ¨‹å£çœŸå—£ãŒå…„弟をå–ã‚Šé•ãˆã¦ã‚‹ã‚ˆã†ãªä¸€æŠ¹ã®ä¸å®‰ã¯æ®‹ã‚‹ã€‚
 
 
  
 ライブドアã®ç›®çš„ã¯ç¤¾é•·ã•ã‚“自身ãŒã“ã†ã‚„ã£ã¦ã¯ã£ãã‚Šã¨è¿°ã¹ã¦ã„ã‚‹ã®ã«ã€ãªã‚“ã§è¦‹å½“外れã®ãŠã‹ã—ãªåˆ†æžã‚’ã—ã¦ã„る輩ã°ã‹ã‚Šãªã‚“ã§ã—ょã†ã‹ã€‚
「è–域化ã•ã‚Œã¦ã„るメディアã®ãƒ–ãƒ©ãƒ³ãƒ‰ã‚’ç ´å£Šã™ã‚‹ãŸã‚ã«ã€ãƒ¡ãƒ‡ã‚£ã‚¢ã‚’è²·ã†ã‚“ã§ã™ã‚ˆã€‚
 ã¾ã•ã«ãƒˆãƒã‚¤ã®æœ¨é¦¬ã€‚å…¥ã£ã¦ã„ã£ã¦ã€ä¸ã‹ã‚‰ãƒœãƒ³ï¼ã¨å£Šã—ã¡ã‚ƒã†ã€‚ã‚‚ã¡ã‚ã‚“ã€ä¸ã«å…¥ã£ãŸæ™‚点ã§ã€ãƒ¡ãƒ‡ã‚£ã‚¢ãŒç¾åœ¨æŒã£ã¦ã„ã‚‹è–域ã®åŠ›ã‚’利用ã—ã¦ã€æˆ‘々ã®ãƒªãƒ¼ãƒã‚’広ã’ã‚‹ã“ã¨ã«ã¯ä½¿ã„ã¾ã™ã‚ˆã€‚ã§ã€ãã®å¾Œã«ã€å£Šã™ã‚“ã§ã™ã‚ˆã€‚
 世間ã®äººãŸã¡ãŒã€Œãªã‚“ã ã€è–域ã ã¨æ€ã£ã¦ã„ãŸã‘ã©ã€ãã‚“ãªã“ã¨ã¯ãªã„ã˜ã‚ƒãªã„ã€ã£ã¦æ„Ÿã˜ã‚‹ã“ã¨ã§ã€è–域化ã•ã‚Œã¦ã„ãŸãƒ‘ワーãŒãªããªã‚‹ã‚ã‘ã§ã™ã‚ˆã€‚æ€ã„上ãŒã£ã¦ã„ãŸãƒ¡ãƒ‡ã‚£ã‚¢ã®è¨˜è€…ãŸã¡ã‚‚ã€ã‚·ãƒ¥ãƒ³ã¨ãªã£ã¡ã‚ƒã†ã‚ã‘ã§ã™ã‚ˆã€‚ã€
 「時代ã¯ãƒ–ãƒã‚°ã‚‹ã€ï¼ˆé ˆç”°ä¼¸è‘—ã€ã‚¢ãƒ¡ãƒ¼ãƒãƒ–ãƒƒã‚¯ã‚¹ï¼‰ã‚ˆã‚ŠæŠœç²‹ã€‚æƒ…å ±ä»•å…¥ã‚Œå…ˆãƒ»ãƒãƒƒãƒˆã¯æ–°èžã‚’殺ã™ã®ã‹blog
 ã¤ã¾ã‚Šã€ã‚ãŸã—ãŒäº‘ã†ã¨ã“ã‚ã®<メディア循環>ã‚’èµ·ã“ã™ã®ãŒæœ€å¤§ã®ç›®çš„ã§ã‚ã‚‹ã‚ã‘ã 。ã ã‹ã‚‰ã€ãƒ•ã‚¸ãƒ†ãƒ¬ãƒ“ã ã¨ã‹ç”£çµŒæ–°èžã ã¨ã‹ã‚ã‚“ãªã‚‚ã®ã‚’手ã«å…¥ã‚Œã¦ä½•ã®å½¹ã«ç«‹ã¤ã®ã‹ãªã‚“ã¦ã“ãŸã©ã†ã§ã‚‚ã„ã„ã‚ã‘ã 。å¤ã„メディアãŒå½¹ã«ç«‹ãŸãªã„ã“ã¨ã‚’証明ã—ã¦å£Šã—ã¦ã—ã¾ã£ã¦ã€æ¬¡ã®ãƒ¡ãƒ‡ã‚£ã‚¢ã®æ™‚代を迎ãˆå…¥ã‚Œã‚‹ãŸã‚ã ã‘ã«ä»•æŽ›ã‘ã‚‹ã®ã ã‹ã‚‰ã€‚
 もã£ã¨ã‚‚ã€å£Šãã†ã¨ã—ã¦ã„ã‚‹ã®ã¯ã‚ãã¾ã§æ—¢å˜ãƒ¡ãƒ‡ã‚£ã‚¢ã®<神話性>ã§ã€å½¹ã«ç«‹ã¤ã‚‚ã®ãŒã‚ã‚‹ã®ãªã‚‰æ‚¦ã‚“ã§ä½¿ã‚ã—ã¦ã‚‚らã†ã¤ã‚‚ã‚Šãªã®ã ã‚ã†ã€‚今回ã®ã‚¦ã‚§ãƒ–上ã®åˆ†æžã§ã€æ—¢å˜ã®ãƒ†ãƒ¬ãƒ“局や新èžç¤¾ã®å½¹ã«ç«‹ãŸãªã•ã‚’ãã¡ã‚“ã¨å‰æã¨ã—ã¦ã„る方々もã€å”¯ä¸€å½¹ç«‹ã¤ã‚‚ã®ãŒã‚ã‚‹ã¨ã—ãŸã‚‰ãã‚Œã¯è¨˜è€…クラブã¸ã®é€šè¡Œæ¨©ã ã¨ã„ã†ã“ã¨ã§ä¸€è‡´ã—ã¦ã„ã‚‹ã¿ãŸã„ã ã—ã€ä¸Šã®ã‚¤ãƒ³ã‚¿ãƒ“ューをèªã‚€é™ã‚Šãƒ›ãƒªã‚¨ãƒ¢ãƒ³ã‚‚ãれを想定ã—ã¦ã„ã‚‹ã®ã ã‚ã†ã€‚
 ã—ã‹ã—ã€ã“ã‚Œã“ãã¾ã•ã—ã神話ã«éŽãŽãªã„。ã‚ã‚“ãªã¨ã“ã‚ã«ä¸€æ¬¡æƒ…å ±ãªã‚“ã¦ã‚‚ã‚“ã¯ãªã„。仮ã«ã‚ã£ã¦ã‚‚ã™ãã«è¡¨ã«å‡ºã‚‹ã—ã€å‡ºã•ãªãゃメディアã¨ã—ã¦ã¯åŠ›ã«ãªã‚‰ãªã„ã—ã€æ˜”ãªã‚‰ã¡ã‚‡ã£ã¨æ—©ã‚ã«å…¥æ‰‹ã™ã‚‹ã“ã¨ã«æ„味ã¯ã‚ã£ãŸã‚“ã ã‚ã†ã‘ã©ã€å„社ã®é€Ÿå ±ãŒä¸¦ã¹ã¦è¦‹ã‚‰ã‚Œã‚‹æ™‚代ã«ãã‚“ãªã‚‚ã®ã¯ãªã‚“ã®æ„味もãªã„。
  ã¡ã‚‡ã£ã¨è©±ã¯é£›ã¶ã‘ã©ã€å¹¼å¥³ãƒ¬ã‚¤ãƒ—被害者統計をアップã—ã¾ã—ãŸã€‚kangaeru2001æ°ã‚‚云ã£ã¦ã„るよã†ã«å¤§å¹…ã«æ¸›ã£ã¦ã„ã¾ã™ã€‚
 昨今ã®ãƒãƒªçŠ¯ç½ªè«‡ç¾©ã®éš†ç››ã®ãªã‹ã§ã“ã‚“ãªåŸºæœ¬çš„ãªãƒ‡ãƒ¼ã‚¿ã‚’見ãŸã“ã¨ãŒãªã„。既å˜ãƒžã‚¹ã‚³ãƒŸã‚‚ã€ãれを批判ã™ã‚‹ã‚¦ã‚§ãƒ–上ã®é¢ã€…ã‚‚ã€ä¸€ç•ªåŸºæœ¬ã®æƒ…å ±ã‚’æŒãŸãšã«æƒ³ã„付ãã§ä½Žãƒ¬ãƒ™ãƒ«ã®è¨€èª¬ã‚’åã„ã¦ã„ã‚‹ã«éŽãŽãªã„。無智ãªã ã‘ã§ã¯ãªãã€ã“ã†ã„ã†æƒ…å ±ã‚’æŽ¢ã—出ãã†ã¨ã‚‚ã—ã¦ã„ãªã„ã¨ã“ã‚ãŒæƒ…ã‘ãªã„。
 ã¡ã‚‡ã†ã©ã„ã¾ã¯åŽ»å¹´ã®è¦å¯Ÿçµ±è¨ˆã®ç™ºè¡¨æ™‚期ã§ã€å„マスコミã¯è¦å¯Ÿã®è¨˜è€…クラブã§ã„ãŸã ã„ã¦ããŸæƒ…å ±ã‚’å…ƒã«ã„ã‚ã„ã‚書ã„ã¦ã‚‹ãŒã€ä¸Šã®å¦‚ãデータを見ã¦ãŠã‚Œã°ã„ã‹ã«å‡ºé±ˆç›®ãªå†…容ã§ã‚ã‚‹ã‹ã™ãã«åˆ¤ã‚‹ã€‚ä¸€æ¬¡æƒ…å ±ã¯è¨˜è€…クラブã§ã¯ãªãã€å€‰åº«ã®ä¸ã§åŸ‹ã‚‚ã‚Œã¦ã„る。ã—ã‹ã‚‚ã€èª°ã§ã‚‚手間ã•ãˆæŽ›ã‘ã‚Œã°å…¥æ‰‹ã§ãã‚‹å½¢ã§ã€‚
 犯罪ã«é–¢ã™ã‚‹æƒ…å ±ã¯å„年分æ–ã•ã‚Œã¦ã¦ã€çŠ¯ç½ªç™½æ›¸ã«ã¾ã¨ã‚られã¦ã„ã‚‹ã®ã¯ãã®æ•°ãƒ‘ーセントã«éŽãŽãªã„。ã»ã‚“ã¨ã«ãŠã‚‚ã—ã‚ã„æƒ…å ±ã¯ä¾ç„¶ã¨ã—ã¦çœ ã£ã¦ã„る。
 ã‚ãŸã—ãŒã€Œå社会å¦è¬›åº§ã€ãªã‚“ã‹ã‚’ã¾ã£ãŸããŠã‚‚ã—ã‚ã„ã¨æƒ³ã‚ãªã„ã®ã¯ã€å‡ºæ¥åˆã®çµ±è¨ˆã‚„分æžã‚’æŒã£ã¦ãã¦ã„ã‚‹ã ã‘ã§ã“ã†ã„ã†æŽ˜ã‚Šèµ·ã“ã—ã‚’ã‚„ã£ã¦ãªã„ã‹ã‚‰ã§ã€ã‚ãŸã—ãŒå°‘年犯罪データベースã§ã‚„ã‚ã†ã¨ã—ã¦ã„ã‚‹ã“ã¨ã¨ä¸€è¦‹ä¼¼ã¦ã„るよã†ã§æ ¹æœ¬çš„ã«é•ã†ã€‚ãªã«ã‚†ãˆæ•°å—ã§ã¯ãªã具体事例ã«åŠ›ã‚’入れã¦ã‚‹ã‹ã¨ã„ã†ã“ã¨ã«ã‚‚ã¤ãªãŒã‚‹ã‚“ã ãŒã€‚
 ã¾ã‚ã€çŠ¯ç½ªç™½æ›¸ãƒ¬ãƒ™ãƒ«ã®æƒ…å ±ã•ãˆæŒãŸãšã«å‡ºé±ˆç›®ãªå¦„想を撒ã散らã—ã¦ã„る輩ãŒå¤šã„ã®ã§ã“ã‚“ãªã‚‚ã®ã«ã‚‚一定ã®å˜åœ¨ä¾¡å€¤ã¯ã‚ã‚‹ã®ã ã‚ã†ãŒã€ã‚‚ã†ã²ã¨ã¤æ·±ã„ã‚‚ã®ãŒæ¬²ã—ã„ã¨ã“ã‚。ウェブ上ã§å‰ãã†ã«æƒ…å ±ã«ã¤ã„ã¦èªžã£ã¦ã„るマスコミ人やら大å¦äººã‚„らã¯ã€ã¾ãšã“ã‚“ãªç°¡å˜ãªãƒ–ツãらã„ã¯ã™ã¹ã¦æŽ˜ã‚Šèµ·ã“ã—ã¦ã‹ã‚‰ä¸€äººå‰ã®å£ã‚’利ã„ã¦ã‚‚らã„ãŸã„ã‚‚ã‚“ã§ã¯ã‚る。
 ã•ã¦ã€æ–°èžã¯ã‚‚ã¨ã‚ˆã‚Šã€ãƒ†ãƒ¬ãƒ“ã‚‚ãŸã ã§ã•ãˆè‹¥ã„ã‚‚ã‚“ã¯ã‚ã‚“ã¾ã‚Šè¦‹ã¦ãªã„ã®ã«åœ°ä¸Šæ³¢ãƒ‡ã‚¸ã‚¿ãƒ«ã‚„ら著作権ä¿è·å¼·åŒ–やら自ら滅ã³ã®é“ã‚’ã¾ã£ã—ãらã§ã€NHKãŒå—信料を払ã£ã¦ãªã„者ã«ã‚¹ã‚¯ãƒ©ãƒ³ãƒ–ルをã‹ã‘ã¦è¦‹ã›ãªã„ãªã‚“ã¦ã“ã¨ã‚’やらã‹ã›ã°æœ¬å½“ã«æ¯ã®æ ¹ãŒåœã¾ã‚‹ã®ã ã‘ã©ã€ã¾ã‚ãã“ã¾ã§å®Œå…¨ã«æ½°æ»…ã›ãšã¨ã‚‚å‹æ‰‹ã«ã“ã‘ã¦ãれるã®ã ã‹ã‚‰ã‚ã–ã‚ã–内部ã«å…¥ã‚Šè¾¼ã‚“ã§å£Šã™å¿…è¦ã‚‚ãªã„ã‹ã¨æƒ³ã‚れる。
 iPodã®æˆåŠŸã¯æ—¢å˜ã®ãƒ¬ã‚³ãƒ¼ãƒ‰ä¼šç¤¾ã¨ã‚½ãƒ‹ãƒ¼ãŒå‹æ‰‹ã«è‡ªæ»…ã—ã¦ãã‚ŒãŸã“ã¨ãŒè¦å› ã®99%ã§ã€ãã“ã«ãã“ãã“ã„ã„別ã®é¸æŠžè‚¢ã‚’æ示ã—ãŸã‹ã‚‰å¾ªç’°ãŒèµ·ã“ã£ãŸã®ã§ã€ã‚¸ãƒ§ãƒ–スãŒæ—¢æˆã®ã‚·ã‚¹ãƒ†ãƒ を壊ã—ãŸã‚ã‘ã§ã¯ãªã„ã®ã ãŒãªã‚“ã¨ãªããã‚“ãªé¢¨ãªæ§‹å›³ã«ãªã£ã¦ã„る。既å˜ã®ã‚‚ã®ã‚’壊ã—ã¦ã‚‚ã€ã©ã£ã¡ã¿ã¡ãã¡ã‚“ã¨æ–°ã—ã„ã‚‚ã®ã‚’用æ„ã—ã¦ã„ãªã„ã¨ã„ã‘ãªã„ã‚“ã ã‹ã‚‰ã€å†…部ã«å…¥ã‚‰ãšæ–°ã—ã„メディアã§æ£é¢ã‹ã‚‰ã¶ã¤ã‹ã£ãŸã»ã†ãŒè©•ä¾¡ã‚‚高ããªã‚‹ã—二度手間ã«ã‚‚ãªã‚‰ãšã‚ˆã‚ã—ã„ã‹ã¨æƒ³ã†ã€‚
 既æˆã®ã‚·ã‚¹ãƒ†ãƒ ã®å†…部ã«å…¥ã‚Šè¾¼ã‚“ã§ã„ã‚‹ã¨ã€ã¸ãŸã™ã‚‹ã¨æ»…ã¶å´ã®è€…ã¨è¦‹ã‚‰ã‚Œã‚‹ã—ã€ã‚¸ãƒ§ãƒ–スもアウトサイダーã®ç«‹å ´ã‚’ä¿ã£ãŸã“ã¨ãŒæˆåŠŸã®ä¸€å› ã¨ãªã£ã¦ã„ã‚‹ã§ã‚ã‚ã†ã€‚ã¾ã‚ã€å£Šã™è€…ã¨ãã“ã‹ã‚‰å¾—られる果実をå—ã‘å–ã£ã¦æ–°ãŸãªä¸–界をæ¡ã‚‹è€…ãŒé•ã†ã¨ã„ã†ã®ã¯æ´å²ä¸ŠãŠã†ãŠã†ã«ã—ã¦ã‚ã‚‹ã“ã¨ã§ã™ãŒã€‚
 ã¤ã¾ã‚Šã€å£Šã—ãŸã‚ã¨ã®æ–°ãŸãªã‚‹ãƒ¡ãƒ‡ã‚£ã‚¢ã¯ã¾ã ã¾ã ã¿ã‚“ãªã«å¹³ç‰ã«é–‹ã‹ã‚Œã¦ã„る。
 既å˜ãƒ¡ãƒ‡ã‚£ã‚¢ã®<神話性>を壊ã™ã ã‘ãªã‚‰å®Ÿéš›ã«è²·ã„å–ã‚‹å¿…è¦ã¯ãªã„ã—ã€ãŠãらããã†ã„ã†ã‚·ãƒŠãƒªã‚ªã‚‚用æ„ã—ã¦ã„ã‚‹ã®ã ã‚ã†ãŒã€ã—ã‹ã—ã€ãƒ›ãƒªã‚¨ãƒ¢ãƒ³ã¯è‡ªåˆ†ã®å¼¾ã ã‘ã§ã‚„ã£ã¦ã‚‹ã‚ã‘ã§ã¯ãªã完全ã«ã‚³ãƒ³ãƒˆãƒãƒ¼ãƒ«ã§ãã‚‹ã‚ã‘ã§ã¯ãªã„ã®ãŒæœ€çµ‚çš„ã«ãƒãƒƒã‚¯ã¨ãªã‚ã†ã€‚メディアã¯ã„ã‹ã«<他者>を排ã—ã¦è‡ªåˆ†ã®å¥½ããªã‚ˆã†ã«å‡ºæ¥ã‚‹ã‹ã«ã‚„ã¯ã‚ŠæŽ›ã‹ã£ã¦ã„る。
 å‰å›žã¡ã‚‡ã£ã¨æ›¸ã忘れãŸã‘ã©ã€ã€Œã“ã‚Œã‹ã‚‰ãƒ†ãƒ¬ãƒ“局を新ã—ã創ã£ã¦ãã‚Œã ã‘ã®è¦–è´çŽ‡ãŒå–れるã®ã‹ã‚ã‚‹ã„ã¯å–ã‚‹ãŸã‚ã«ã‚³ã‚¹ãƒˆãŒã©ã‚Œã ã‘掛ã‹ã£ã¦å›žåŽã§ãã‚‹ã®ã‹ã€ã¨ã„ã†ã®ã¯è©±ã®å‰æã¨ã—ã¦é›»é€šã ã¨ã‹ãã®æ‰‹ã®å¤–部ã®é‚ªé”者を排ã—ãŸä¸Šã§ã§ãã‚‹ã‹ã©ã†ã‹ã¨ã„ã†ã“ã¨ã§ã€ãã‚“ãªæ¨ªã‚„ã‚ŠãŒç›¸å¤‰ã‚らãšå…¥ã‚‹ã®ãªã‚‰ãƒ¡ãƒ‡ã‚£ã‚¢ãªã‚“ã‹è‡ªã‚‰æŒãŸãªã„ã§ä¸‹è«‹ã‘ã§åˆ¶ä½œã—ã¦ã„ã¦ã‚‚ã¹ã¤ã«åŒã˜ã‚ã‘ã§ã™ã‹ã‚‰ã€‚考ãˆã¦ã¿ã‚Œã°ãƒ†ãƒ¬ãƒ“å±€ãªã‚“ã¦ã‚ã‚“ãªã—ãŒã‚‰ã¿ã らã‘ã®ã‚‚ã®ãŒãƒ¡ãƒ‡ã‚£ã‚¢ã¨ã—ã¦ã¯ã¨ã‚‚ã‹ãã€ã‚ˆãã‚‚ã„ã¾ã¾ã§å•†å£²ã¨ã—ã¦æˆã‚Šç«‹ã£ã¦ã„ãŸã‚‚ã‚“ã 。
 既å˜ã®ãƒ†ãƒ¬ãƒ“局やら新èžç¤¾ã‚„ら手ã«å…¥ã‚Œã¦ã©ã†ã™ã‚‹ã®ã‹ãªã‚“ã¦ã“ã¨ã‚’分æžã™ã‚‹ã‚ˆã‚Šã‚‚ã€æ™‚代ã«ç«‹ã¡ä¼šã£ãŸè€…ã¨ã—ã¦è€ƒãˆãã°ãªã‚‰ã‚“ã“ã¨ã¯ã»ã‹ã«ã‚ã‚‹ã¨ã„ã†ã“ã¨ã§ã™ã€‚
 果ãŸã—ã¦ãã‚Œã¯ã“ã‚“ãªæµã‚Œã®å»¶é•·ç·šä¸Šã«ã‚ã‚‹ã®ã‚„らãªã„ã®ã‚„ら。
2/14追記
 ã‚ã‚„?ã“れをèªã‚€ã¨ãƒ›ãƒªã‚¨ãƒ¢ãƒ³ã¯ã„ã¾ã‚ã–ã‚ã–æ–°èžã‚’出ã™æ„味もã€è¨˜è€…クラブã«ã¤ã„ã¦ã‚‚よã判ã£ã¦ã‚‹ã‚„ん。ã¾ã™ã¾ã™å‰å›žã®æ–‡ç« を書ãã‚“ã˜ã‚ƒãªã‹ã£ãŸãªã€‚
 ãƒãƒƒãƒˆãƒ»ã‚¸ãƒ£ãƒ¼ãƒŠãƒªã‚ºãƒ ã¨ã‚„らã§é¨’ã„ã§ãŸé€£ä¸ã‚ˆã‚Šã€ãã‚“ãªã®ã«èˆˆå‘³ã®ãªã„ホリエモンã®ã»ã†ãŒãƒ¡ãƒ‡ã‚£ã‚¢ã®ã“ã¨ã‚’よã見通ã—ã¦ã„ã‚‹ã¨ã¯ã©ã†ã„ã†ã“ã¨ã‚ˆã€‚ã ã„ãŸã„ã€ãƒãƒƒãƒˆãƒ»ã‚¸ãƒ£ãƒ¼ãƒŠãƒªã‚ºãƒ ã¨ã‚„らã®è°è«–ã§ã“ã‚“ãªé‡è¦ãªæƒ…å ±ã‚’ã¾ã£ã•ãã«ä¼ãˆã¦ãã‚Œã¦ãŸã‚‰ã‚ãŸã—ã‚‚ã‚ã‚“ãªã®æ›¸ã‹ãªã‹ã£ãŸã®ã«ã¨ã€ãƒãƒƒãƒˆã¯æ–°èžã‚’殺ã™ã®ã‹blogを見るã¨å˜ã«å½¼ã‚‰ã‚‚è˜ã‚‰ãªã‹ã£ãŸã¿ãŸã„ã€ã£ã¦ãªã‚“ã˜ã‚ƒãら。世ã®ä¸ã©ãƒ¼ãªã£ã¨ã‚“ã®ã€‚
 世間ã§ã¯ãƒãƒƒãƒˆãƒ»ã‚¸ãƒ£ãƒ¼ãƒŠãƒªã‚ºãƒ ã¨ã‚„らã®è°è«–ãŒãŠç››ã‚“ãªã‚ˆã†ã§ã€ãã‚Œã¯ãã‚Œã§å¤§åˆ‡ãªã“ã¨ã§ã‚‚ã‚ã‚‹ã‚“ã§ã—ょã†ãŒã€ã™ãã‚ŒãŸæ›¸ã手ã¯æœ¬ã§ã‚‚æ–°èžã§ã‚‚ãƒãƒƒãƒˆã§ã‚‚ã„ã‚ã„ã‚å‹æ‰‹ã«ã‚„ã£ã¦ã„ãã“ã¨ã§ã—ょã†ã‹ã‚‰ã€ã‚ã‚“ã¾ã‚Šã‚¦ã‚§ãƒ–特有ã®è©±ã§ã‚‚ãªã„。
 新èžã‚„雑誌ã¯å£²ã‚Œãªããªã£ã¦ã€ã¨ãã«æ–°èžã¯ã„ã¾ã©ãã‚ã‚“ãªã‚‚ã®ã‚’èªã‚“ã§ãれる呑気ãªå›£å¡Šä¸–代ã®æ¶ˆæ»…ã¨ã¨ã‚‚ã«æ¥æ…‹ã‚’変ãˆã–ã‚‹ã‚’å¾—ãªã„ã§ã—ょã†ã‹ã‚‰åˆ‡ã‚Šæ¨ã¦æ±ºå®šæ¸ˆã¿ã®æœ«ç«¯ã®è¨˜è€…ã•ã‚“ãªã‚“ã‹ã«ã¯æ»æ´»å•é¡Œãªã‚“ã§ã—ょã†ãŒã€ã‚¦ã‚§ãƒ–全体ã®ã€ã‚ã‚‹ã„ã¯ã‚¦ã‚§ãƒ–ã®æœ¬è³ªçš„ãªè©±ã¨ã—ã¦ã¿ãªã•ã‚“ãŒèˆˆå‘³ã‚’æŒã£ãŸã‚Šã™ã‚‹ã®ã¯ã‚ã‚“ã¾ã‚Šå¥å…¨ãªã“ã¨ã§ã¯ãªã„ã¨æ„šè€ƒã—ã¾ã™ã€‚
 ã¡ã‚‡ã£ã¨ã ã‘触れã¦ãŠãã¾ã™ã¨ã€ä¸æ€è°ã ã£ãŸã®ã¯ã‚¦ã‚§ãƒ–ã¯å„²ã‹ã‚‰ãªã„ã¨ã‹è¦–è´çŽ‡ã§è¦‹ã‚‹ã¨2ã¡ã‚ƒã‚“ã§ã•ãˆ1.6%程度ã¨ã‹ã„ã†è©±ãŒã‚ã£ãŸã“ã¨ã§ã€ã‚‚ã—æ–°èžãŒå„²ã‹ã‚‹ã®ãªã‚‰æ–°ã—ãæ–°èžç¤¾ã‚’èµ·ã“ã›ã°ã„ã„ã—ã€ã“ã‚Œã‹ã‚‰ãƒ†ãƒ¬ãƒ“局を新ã—ã創ã£ã¦ãã‚Œã ã‘ã®è¦–è´çŽ‡ãŒå–れるã®ã‹ã‚ã‚‹ã„ã¯å–ã‚‹ãŸã‚ã«ã‚³ã‚¹ãƒˆãŒã©ã‚Œã ã‘掛ã‹ã£ã¦å›žåŽã§ãã‚‹ã®ã‹ãŒå•é¡Œã®ã¯ãšã§ã€ã©ã†ã‚‚比較対象ãŒãŠã‹ã—ã„ã—ウェブã‹ã©ã†ã‹ã¯é–¢ä¿‚ãªã„。
 既å˜ã®ãƒžã‚¹ã‚³ãƒŸãŒç¡¬ç›´ã—ã¦ã„ã‚‹ã¨ã‹é£Ÿã„扶æŒãŒæ¸›ã‚‹ã¨ã‹ã“ã‚Œã‹ã‚‰ã‚¸ãƒ£ãƒ¼ãƒŠãƒªã‚¹ãƒˆã¨ã—ã¦å£²ã‚Šå‡ºã—ãŸã„ã¨ã‹ã„ã†è©±ã¯ã‚¦ã‚§ãƒ–云々ã¨é–¢ä¿‚ãªãã€ã¾ãšæ–°ã—ãæ–°èžç¤¾ãªã‚Šãƒ†ãƒ¬ãƒ“å±€ãªã‚Šã‚’èµ·ã“ã—ã¦è‡ªåˆ†ã§ãƒ¡ãƒ‡ã‚£ã‚¢ã‚’æ¡ã£ã¦è§£æ±ºã™ã‚‹ã®ãŒã‚¹ã‚¸ã§ã€ãã‚Œã¯é‡‘や手間ãŒæŽ›ã‹ã‚ŠéŽãŽã¦äº‹å®Ÿä¸Šä¸å¯èƒ½ã€ãã‚Œãªã‚‰é£¼ã„犬ã¨ã—ã¦ãªã‚“ã¨ã‹ã—ãŒã¿ã¤ã„ã¦å®šå¹´ã¾ã§å ªãˆå¿ã¶ã‹ã€ã‚ã‚‹ã„ã¯ãƒãƒƒãƒˆãƒ»ã‚¸ãƒ£ãƒ¼ãƒŠãƒªã‚ºãƒ ã¨ã‚„らã¯ã¨ã‚Šã‚ãˆãšé‡‘ã¯æŽ›ã‹ã‚‰ã‚“ã‹ã‚‰å¯èƒ½ã‹ã‚‚ã£ã¦è©±ã«ãªã£ã¦ã‚‹ã¯ãšãªã®ã«ãªã«ã‚„らè°è«–ãŒè»¢å€’ã—ã¦ãŠã‚‹ã€‚
 ã‚ãŸã—ã¯æ–°ã—ã„æ–°èžç¤¾ãŒã“ã‚Œã‹ã‚‰å‡ºã¦ãã‚‹ã¹ãã ã¨è€ƒãˆã¦ãŠã‚Šã¾ã—ã¦ã€ãŸã¨ãˆã°æ”¿æ²»çµŒæ¸ˆå°‚é–€ã®ãƒ•ãƒªãƒ¼ãƒšãƒ¼ãƒ‘ーをã“ã•ãˆã¦ç‰¹å®šã®é§…ã§é€šå‹¤å®¢ã«ãŸã ã§é…ã‚‹ãªã‚“ã¦ã“ã¨ã‚’やらã‹ã›ã°ã€é›»è»Šã«åŠã‚Šåºƒå‘Šã‚’出ã—ã¦æºå¸¯å‘ã‘ブãƒã‚°ã‚’発信ã™ã‚‹ãªã‚“ã¦ã‚ˆã‚Šã‚‚商売ã¨ã—ã¦ã‚‚廻るå¯èƒ½æ€§ãŒã‚るやも知れんã—ã€å½±éŸ¿åŠ›ã‚‚æŒã¦ã‚‹ã‚„も知れん。
 駅売り新èžã‚’駆é€ã—ã¦ã—ã¾ãˆã‚‹ã®ãªã‚‰ãã®åºƒå‘Šã¯ã©ã“ã‹ã«ç§»ã‚‹ã‚“ã ã‹ã‚‰ã€æ¼«ç„¶ã¨å¤‰åŒ–ã‚’å¾…ã£ã¦ã‚‹ã‚ˆã‚Šã‚‚ã¦ã£ã¨ã‚Šæ—©ã„ã—ã€ç„¡æ–™ã§ã‚‚駆é€ã§ããªã„内容ãªã‚‰å…ƒã‹ã‚‰è°è«–ã™ã‚‹ã»ã©ã®ã“ã¨ã§ã¯ãªããªã‚‹ã€‚æ—¢å˜ã®ãƒ–ãƒã‚°ã®è¨˜äº‹ã§ã‚‚è²·ã„集ã‚ã¦èª°ã‹ã‚„ã£ã¦ã¿ã¾ã›ã‚“ã‹ã。ã‚ã‚‹ã„ã¯æ—¢å˜ã®æ–°èžã®è¨˜äº‹ã®é–“é•ã„ã‚’ã²ã¨ã¤ã²ã¨ã¤æŒ‡æ‘˜ã™ã‚‹å†…容をãã®æ—¥ã«é…ã‚‹ã¨ã‹ã€‚
 ã„ã‚„ã€ã¹ã¤ã«æ™®é€šã®æ–°èžã§ã‚‚ã„ã„ã‚“ã§ã™ãŒã€æ–°ã—ãèµ·ã“ã›ã°<スーツ>を排ã—ã¦è‡ªåˆ†ã§ãƒ¡ãƒ‡ã‚£ã‚¢ã‚’æ¡ã£ã¦è‡ªåˆ†ã®è²¬ä»»ã§å¥½ããªã‚ˆã†ã«æ›¸ã‘る。紙ã‹é›»åã‹ã¯é–¢ä¿‚ãªãã“ã†ã„ã†ãƒ¡ãƒ‡ã‚£ã‚¢ã®ã‚りよã†ãŒå•é¡Œãªã‚ã‘ã§ã€ãªã«ã‚„ら新ã—ã„機能ãŒå•é¡Œã®ã‚ˆã†ã«å—ã‘å–られるウェブã§ã‚„るより新èžã§ã‚„ã‚‹ã»ã†ãŒã¯ã£ãã‚Šã—ã¾ã™ã®ã§ã€‚
 ãã‚Œã¯ã•ã¦ãŠãã€ã‚ãŸã—ã¯ã“ã‚“ãªå°‘æ•°ã®ç™ºä¿¡è€…ã®ã“ã¨ã‚ˆã‚Šã‚‚ウェブ特有ã®è©±ã¨ã—ã¦å—ã‘手ã®æ–¹ã«èˆˆå‘³ãŒã‚ã‚Šã¾ã™ã€‚
 2002/9/25 平å‡å¯¿å‘½23æ³ã‚‚ã€æœ¬ã‚„åšç‰©é¤¨ã§ã“ã‚“ãªèŽ«è¿¦ãªã“ã¨ã‚’云ã£ã¦ã¾ã™ã‚ˆã¨ã„ã†ç™ºä¿¡è€…å´ã®ã“ã¨ã‚’å•é¡Œã«ã—ã¦ã„ã‚‹ã®ã§ã¯ãªãã€ã“ã‚“ãªèŽ«è¿¦ãªè©±ã‚’鵜呑ã¿ã«ã—ã¦ã„る方々ãŒã„ã£ã±ã„ã„ã‚‹ã“ã¨ãŒæ¤œç´¢ã—ã¦ã¿ã‚‹ã¨ã¯ã£ãり判るã€ã¾ã£ãŸã便利ãªä¸–ã®ä¸ã«ãªã£ãŸã‚‚ã‚“ã ãªã‚ã¨ã„ã†ã“ã¨ãŒä¸€ç•ªäº‘ã„ãŸã‹ã£ãŸã®ã§ã—ãŸã€‚æƒ…å ±ã®å—ã‘手ã®è„³å†…ã‚’ã“ã‚Œã»ã©ã¾ã¨ã¾ã£ãŸæ•°ã§è¦—ãã“ã¨ã¯ã‚¦ã‚§ãƒ–ãŒç”Ÿã¾ã‚Œã‚‹å‰ã«ã¯ä¸å¯èƒ½ã ã£ãŸã®ã§ã™ã‚ˆã€‚
 2001/9/29 誰ã‹ãŒã‚µãƒœã£ã¦ã‚‹ã‚‚ã€æµ·å¤–ã®ã™ãã‚ŒãŸã‚µã‚¤ãƒˆã‹ã‚‰æƒ…å ±ã‚’ã„ãŸã ã„ã¦ãã¦ã‚¸ãƒ£ãƒ¼ãƒŠãƒªã‚ºãƒ ã‚’ã‚„ã‚Šã¾ã—ょã†ã¨ã„ã†ã‚ˆã‚Šã‚‚ã€ã”ã普通ã®æ–¹ã€…ã®æ„è˜ãŒã©ã®ã‚ãŸã‚Šã«ã‚ã‚‹ã®ã‹ã€åœ°å›³ã‚’æããŸã‚ã®åŸºç¤Žãƒ‡ãƒ¼ã‚¿ãŒæ¬²ã—ã„ã¨ã„ã†è©±ãªã®ã§ã™ã€‚
 海外ã®ã™ãã‚ŒãŸãƒ–ãƒã‚°ã‚„ãŠã‚‚ã—ã‚ブãƒã‚°ãªã‚“ã‹ã‚’紹介ã™ã‚‹ã‚µã‚¤ãƒˆã¯ã„ã£ã±ã„ã§ãã¾ã—ãŸãŒã€ç§ã®æ¬²ã™ã‚‹ã‚‚ã®ã¯ãªã„よã†ã§ã™ã€‚ã‚ã‚Œã»ã©ãŠé¡˜ã„ã—ã¦ãŠã„ãŸã®ã«ã€ä¸æ±ã®æ™®é€šã®æ–¹ã€…ã®ãƒ–ãƒã‚°ã¯èª°ã‚‚æ•™ãˆã¦ãれんã—。国内ã®ãƒ–ãƒã‚°ã§ã‚‚ã”ã普通ã®æ–¹ã€…ã®æ„è˜ã‚’ã¾ã¨ã‚ãŸã‚ˆã†ãªã‚µã‚¤ãƒˆã¯ã‚ã‚Šã¾ã™ã§ã—ょã†ã‹ã€‚
 トラックãƒãƒƒã‚¯ã‚’辿ã£ã¦è¤‡æ•°ã®ãƒ–ãƒã‚°ã«ã¾ãŸãŒã‚‹è°è«–をツリー状ã«è¡¨ç¤ºã™ã‚‹ãƒ—ãƒã‚°ãƒ©ãƒ ãªã‚“ã‹ã¯ã‚ã£ã¦ã€é †ç•ªã«è°è«–ã‚’èªã‚€ã«ã¯ä¾¿åˆ©ã§ã™ãŒã€ã‚‚ã£ã¨å¤§ãã人々ã®æ„è˜ã®åˆ†å¸ƒãŒåˆ¤ã‚‹ã‚ˆã†ãªã²ã¨ã¤ã®è°è«–ã«å¯¾ã™ã‚‹ãƒ–ãƒã‚°ã®é³¥çž°çš„ãªç›¸é–¢å›³ã€ã‚ã‚‹ã„ã¯å€‹ã€…ã®ãƒ–ãƒã‚°ãªã‚“ã‹ã¯é–¢ä¿‚ãªããã‚Œãžã‚Œã®èªè€…æ•°ã‚’å…ƒã«ã—ãŸã‚¦ã‚§ãƒ–ã§ã®æ„è˜åˆ†å¸ƒãŒè‰²ã®é•ã„ã§ä¸€ç›®ã§åˆ¤ã‚‹åˆ†åé‹å‹•å›³ãªã‚“ã¦ã®ãŒæ—©ã欲ã—ã„ã¨ã“ã‚ã§ã™ã€‚ãれも時々刻々ã¨ãƒªã‚¢ãƒ«ã‚¿ã‚¤ãƒ ã§è‰²ã®åˆ†å¸ƒãŒå¤‰è»¢ã—ã¦ã„ãã‚‚ã®ã§ã‚ã£ãŸãªã‚‰ã€‚
 もã¡ã‚ã‚“ã“ã‚“ãªã‚‚ã®ãŒã§ããŸãªã‚‰ãã‚Œã«å½±éŸ¿ã•ã‚Œã¦è‡ªåˆ†ã®è¨˜äº‹ã‚’変ãˆãŸã‚Šã€æƒ…å ±æ“作ã™ã‚‹è¼©ã‚‚出ã¦ãã‚‹ã§ã—ょã†ãŒã€ãã‚Œã“ã時代ãŒå¤‰ã‚ã£ãŸã“ã¨ãŒå®Ÿæ„Ÿã§ãã‚‹ã¨ã„ã†ã‚‚ã®ã§ã€‚
 ä¼æ¥ã‚„政府ã¯äººã€…ã®æ„è˜ã‚’掴むãŸã‚ã«ãƒ–ãƒã‚°ãªã‚“ã‹ã‚’ã©ã®ç¨‹åº¦èª¿æŸ»ã—ã¦ã„ã‚‹ã®ã§ã—ょã†ã‹ã€‚ジャーナリズムãªã‚“ã¦ã“ã¨ã‚ˆã‚Šã‚‚ã€ãƒãƒªãƒ»ã‚»ãƒ«ãƒ€ãƒ³ã®å¿ƒç†æ´å²å¦ã®åŸºç¤Žãƒ‡ãƒ¼ã‚¿ã¿ãŸã„ãªã‚‚ã®ã¨ã—ã¦ã®ã‚¦ã‚§ãƒ–ã®ã»ã†ãŒã‚ãŸã—ã«ã¯èˆˆå‘³ãŒã‚る。絶望書店日記ã§ã¯ä¸€è²«ã—ã¦ã“ã®ã“ã¨ã‚’è¿°ã¹ã¦ããŸã®ã§ã—ãŸã€‚
 ãƒãƒªãƒ»ã‚»ãƒ«ãƒ€ãƒ³ã®ç†è«–ã§ã¯è¦³æ¸¬å¯¾è±¡ã®äººã€…ãŒå¿ƒç†æ´å²å¦ã®ä»•çµ„ã¿ã‚’è˜ã‚‰ãªã„ã“ã¨ãŒå¿ƒç†æ´å²å¦æˆç«‹ã®è¦ä»¶ã¨ãªã£ã¦ãŠã‚Šã¾ã™ãŒã€ã“ã‚“ãªå‰æã¯ãŠã‹ã—ã„ã®ã§ã€çš†ãŒã‚¹ã‚³ã‚¢ãƒœãƒ¼ãƒ‰ã‚’見ãªãŒã‚‰é™£åœ°ã‚’å–ã‚Šåˆã†ã»ã†ãŒãŠã‚‚ã—ã‚ã„ã¨ã„ã†ã‚‚ã®ã€‚ã‚‚ã¡ã‚ん政府ã«ã‚‚プレイヤーã®ã²ã¨ã‚Šã¨ã—ã¦å‚åŠ ã—ã¦ã‚‚らã£ã¦ã€‚
 全体ã®åœ°å›³ã‚’æãã®ã¯é“é ã—ã§ã‚ã‚Šã¾ã™ãŒã€ã¨ã‚Šã‚ãˆãšæœ‰åŠ›ãƒ–ãƒã‚°ã¯ã‚³ãƒ¡ãƒ³ãƒˆæ¬„ã«æ„šã«ã‚‚付ã‹ãªã„書ãè¾¼ã¿ã‚’ã—ã¦ã‚‚らã†ã‚ˆã‚Šã‚‚ãã®æ–¹ã€…ã«ãƒˆãƒ©ãƒƒã‚¯ãƒãƒƒã‚¯å…ˆã®ãƒ–ãƒã‚°ã‚’分類ã—ã¦ã‚‚らã£ãŸã‚Šã€ã‚ã‚‹ã„ã¯ãƒˆãƒ©ãƒƒã‚¯ãƒãƒƒã‚¯ã«è³›æˆã‹å対ã‹ãらã„ã¯è¡¨æ˜Žã™ã‚‹æ©Ÿèƒ½ã‚’æŒãŸã›ãªã„ã“ã¨ã«ã¯æ„味付ã‘ウェブãªã‚“ã¦ã®ã¯ã¨ã¦ã‚‚辿りã¤ã‘ã‚“ã‘ã©ã€ã“ã®æ‰‹ã®å–り組ã¿ã¯ã©ã†ãªã£ã¦ã„ã‚‹ã®ã§ã—ょã†ã‹ã€‚
 今月ã‹ã‚‰ãƒ†ã‚¯ãƒŽãƒ©ãƒ†ã‚£ã¨ã‹ã„ã†ã®ãŒã‚¢ãƒ¡ãƒªã‚«ã•ã‚“ã‹ã‚‰ã‚„ã£ã¦ãã¦ã€å€‹ã€…ã®ãƒ–ãƒã‚°ã®ä½ç½®ä»˜ã‘機能も多少ã¯ã‚ã‚‹ãã†ãªã‚“ã§ã™ãŒã€ã‚ã¡ã‚‰ã•ã‚“ã®ã‚µãƒ¼ãƒ“スã«é ¼ã‚‹ã®ã¯ã„ã•ã•ã‹æƒ…ã‘ãªã„。ã©ã†ã›ãªã‚‰æš‡ãªæ–¹ã€…ã«æ•°ãˆãŸã‚Šåˆ†é¡žã—ãŸã‚Šã—ã¦ã‚‚らã†ä½œæ¥ã‚’ã„ã‹ã«ã—ãŸã‚‰ã‚„ã£ã¦ã‚‚らãˆã‚‹ã®ã‹æ‘¸ç´¢ã—ãŸã»ã†ãŒã„ã„よã†ãªæ°—ãŒã—ã¾ã™ã€‚ã“ã†ã„ã†å—ã‘手ã«ã©ã†ã‚„ã£ã¦è¡Œå‹•ã‚’èµ·ã“ã•ã›ã‚‹ã‹ã‚’実験ã™ã‚‹ã«ã‚‚ウェブã¯åˆ¤ã‚Šã‚„ã™ã„ã§ã™ã‹ã‚‰ã€‚ãƒã‚¤ãƒ³ãƒˆã‚’出ã›ã°ãã‚Œã ã‘ã§ã„ã„よã†ãªæ°—ã‚‚ã™ã‚‹ã®ã§ã™ãŒã€‚
 もã¡ã‚ã‚“ã€ãƒãƒƒãƒˆãƒ»ã‚¸ãƒ£ãƒ¼ãƒŠãƒªã‚ºãƒ やブãƒã‚°ã‚’å·¡ã‚‹è°è«–ã«ã¯å—ã‘手ã®ã“ã¨ã‚‚å«ã¾ã‚Œã¦ã¯ã„ã‚‹ã®ã§ã™ãŒã€æ”¹ã‚ã¦ã¡ã‚‡ã£ã¨å¼·èª¿ã—ã¦ãŠããŸã‹ã£ãŸã®ã¨ã€ã‚¸ãƒ£ãƒ¼ãƒŠãƒªã‚¹ãƒˆã‚„らå¦è€…やらブãƒã‚¬ãƒ¼ã‚„らå‰ãã†ã«ã‚¦ã‚§ãƒ–ã‚„ã‚‰æƒ…å ±ã«ã¤ã„ã¦èªžã£ã¦ã„る方々ãŒã¡ã‚‡ã£ã¨æ‰‹é–“を掛ã‘ã‚Œã°æ•°ãˆãŸã‚Šåˆ†é¡žã—ãŸã‚Šã§ãã‚‹ã‚‚ã®ã‚’やらãšã«é©å½“ãªå°è±¡ã ã‘ã§è¦‹å½“外れã®ã“ã¨ã‚’発信ã—ã¦ã„ã‚‹ã®ã§ã¯ã¨ã€æ˜”ã®äº‹ä»¶ã‚„統計ãªã‚“ã‹ã‚’データ化ã—ã¦ã„ã¦ã¤ãã¥ãã¨æƒ³ã£ãŸã‚‚ã®ã§ã™ã‹ã‚‰ã€‚
 ã„ã‹ã«è†¨å¤§ãªé‡ã§ã‚‚ã‚„ã£ã¦ã¿ã‚Œã°ãªã‚“ã¨ã‹ãªã‚‹ã‚‚ã‚“ã§ã€ã©ã†ã›ã‚¦ã‚§ãƒ–やらã«ã¤ã„ã¦ã‚ã‚Œã“れ語ã£ã¦ã„るよã†ãªè¼©ã¯æš‡äººãªã‚“ã ã—。
1/3追記
 ã‚ã‚„?ã“れをアップã—ãŸç›´å¾Œã«ã€Œã‚½ã‚¦ãƒ«ã®åœ°ä¸‹é‰„ã§ã¯ç„¡æ–™æ–°èžãŒå¤§äººæ°—ã€ãªã‚“ã¦ãªè¨˜äº‹ãŒãƒ¤ãƒ•ãƒ¼ã«å‡ºã¨ã‚‹ã‚„ã‚“ã‹ã€‚韓国ã®ã“ã¨ãªã‚“ã‹è˜ã‚‰ã‚“ã‹ã£ãŸã€‚ã“ã‚“ãªã®æ›¸ãã‚“ã˜ã‚ƒãªã‹ã£ãŸãªã€‚ãŠæ¥ãšã‹ã—ã„。
 æ£æœˆæ—©ã€…シンクãƒãƒ‹ã‚·ãƒ†ã‚£ãƒ¼ã«ã—ã¦ã‚„られるã®å›³ã€‚
 よã†ã‚„ãã«ã—ã¦å°‘年犯罪データベースã¯ã¦ãªãŒã¯ã˜ã¾ã‚Šã¾ã—ãŸã€‚コメントãªã‚Šãƒˆãƒ©ãƒƒã‚¯ãƒãƒƒã‚¯ãªã‚Šå¤§ã„ã«ã‚„ã£ã¦ã„ãŸã ã‘ã‚Œã°å¹¸ã„。
 ããšãã™ã—ã¦ã„ã‚‹ã†ã¡ã«ã€ã¯ã¦ãªãŒãªã‚“ã‹å¦™ãªå…·åˆã«ãªã£ã¦ãŠã‚Šã¾ã™ãŒã€ã„ã‚ã„ã‚検討ã—ã¦kangaeru2001æ°ã¯ä½æ‰€ç™»éŒ²ã¯ã›ãšã«ã€ç™»éŒ²æŠ¹æ¶ˆã•ã‚ŒãŸã‚‰ã‚ˆãã«ç§»ã‚‹ã¨ã„ã†ã“ã¨ã«ãªã‚Šã¾ã—ãŸã€‚ã‚‚ã¨ã‚‚ã¨ã€ã‚ã¡ã“ã¡ã®ã‚³ãƒŸãƒ¥ãƒ‹ãƒ†ã‚£ãƒ¼ã«ã‚¢ãƒƒãƒ—ã™ã‚‹äºˆå®šã ã£ãŸã®ã§ã™ãŒã€ãã‚“ãªã‚„ã‚Šã‹ãŸã‚’ã†ã–ã„ã¨æ„Ÿã˜ã‚‹æ–¹ã‚‚ãŠã‚‹ã“ã¨ã§ã—ょã†ã—ã€ã‚€ã—ã‚ã„ã„å£å®ŸãŒã§ããŸã¨æƒ³ã£ã¦ãŠã£ãŸã‚‰ã€ã¾ãŸã‚‚ã‚„ã¯ã¦ãªã®æ–¹é‡ãŒæºã‚‰ã„ã§ã„るよã†ã§å›°ã£ãŸã‚‚ã‚“ã§ã™ã€‚
 ã„ã¾å°‘年犯罪データベースãŒã‚るサーãƒã§MTãªã‚“ã‹ã®ãƒ–ãƒã‚°ã‚’独自ã«ã‚„ã‚‹ã®ã§ãªãコミュニティーã«æŠ¼ã—込むã¨ã„ã†ã®ã¯ã€å°‘年犯罪ã«èˆˆå‘³ã®ãªã„æ–¹ã«ã‚‚見ã¦ã„ãŸã ããŸã„ã¨ã„ã†ã“ã¨ã§ã—ã¦ã€ãã‚‚ãã‚‚kangaeru2001æ°ã‚‚ã‚ãŸã—も少年犯罪ãªã©èˆˆå‘³ã¯ãªãã€æƒ…å ±ã¨ã„ã†ã‚‚ã®ã®æ ¹æºã€å¾“æ¥ã®ãƒ¡ãƒ‡ã‚£ã‚¢ã«å¯¾ã™ã‚‹ã¹ãウェブã®ã‚ã‚Šã‹ãŸã«é–¢ã‚る祕鑰ãŒã“ã“ã«ã‚ã‚‹ã®ã§ãªã„ã‹ã¨è€ƒãˆã¦ã“ã†ã„ã†ã“ã¨ã‚’ã‚„ã£ã¦ã„ã¾ã™ã€‚
 å”力ã—ã¦ã„ãŸã ã„ã¦ã„る方もã™ã¹ã¦å°‘年犯罪ãªã©ã«ã¯èˆˆå‘³ãªãã€ãã®æ–¹é¢ã®å°‚門家ã¯ãŸã å•ã„åˆã‚ã›ã‚’ã—ã¦ãã‚‹ã ã‘ã§ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿ä½œæˆãªã©ã«ã¯1人もå‚åŠ ã›ãšã€ã¾ãŸã»ã¨ã‚“ã©ã®æ–¹ã¯å•ã„åˆã‚ã›ã•ãˆã›ãšã«ä½•ã®åŸºæœ¬çš„æƒ…å ±ã‚‚æŒãŸãªã„ã¾ã¾å°‘年犯罪ã«ã¤ã„ã¦å‰ãã†ã«èªžã£ã¦ã„ãŸã‚Šã—ã¾ã™ã€‚
 ã¯ãŸã¾ãŸã€æ˜”ã®ã»ã†ãŒå°‘年犯罪ã¯å¤šã‹ã£ãŸã¨äº‘ã†æ–¹ã‚‚ã€æ˜”ã¯å°‘年犯罪ã¯å ±é“ã•ã‚Œãªã‹ã£ãŸã€å°‘å¹´ã®ã“ã¨ã‚’考ãˆã¦ã‚€ã—ã‚éš ã•ã‚ŒãŸã¨ã„ã†ã‚ˆã†ãªã“ã¨ã‚’ã®ãŸã¾ã£ãŸã‚Šã™ã‚‹ã“ã¨ãŒã‚ã‚Šã¾ã™ãŒã€ã“ã‚Œã¯æ˜Žã‚‰ã‹ã«é–“é•ã„ã§ã™ã€‚ã„ã¾ã»ã©é€£æ—¥å¤§é¨’ãŽã™ã‚‹ã¨ã„ã†ã“ã¨ã¯ã‚ã‚Šã¾ã›ã‚“ãŒã€å°‘ãªãã¨ã‚‚発覚ã—ãŸã¨ãã®ç¬¬ä¸€å ±ã¯ã€Œåä¾›ãŒäººã‚’殺ã—ãŸï¼ã€ã¨ã§ã‹ã§ã‹ã¨å‡ºã¾ã™ã€‚
 æã‚‹ã¹ã事ã«ã¿ã‚“ãªãã‚“ãªæƒ…å ±ã¯ãã‚Œã„ã«å¿˜ã‚Œã¦ã—ã¾ã†ã®ã§ã™ã€‚ã©ã†ã—ã¦ã“ã‚“ãªã“ã¨ãŒèµ·ãã‚‹ã®ã‹ã€‚
 例ãˆã°ã€æ˜å’Œ52å¹´(1977).10.13〔2æ³å¥³åãŒã‚«ãƒŸã‚½ãƒªã§èµ¤ã¡ã‚ƒã‚“ã®é¡”を切り刻ã¿æ®ºå®³ã€•ãªã‚“ã¦ã®ã‚‚å„紙大ãã扱ã‚ã‚Œã¦ã¾ã™ãŒã€ã„ã¾è¦šãˆã¦ã„ã‚‹æ–¹ã¯ã¯ãŸã—ã¦å¹¾äººã„ã‚‹ã“ã¨ã§ã—ょã†ã‹ã€‚ã“ã®æ™‚代ã«æ–°èžã‚’èªã‚“ã§ã„ãŸã§ã‚ã‚ã†å‘¨ã‚Šã®äººã«è¨Šã„ã¦ã¿ã¦ãã ã•ã„。ã„ã£ãŸã„æ–°èžå ±é“ã¨ã¯ã‚ã‚Œã¯ãªã‚“ã§ã‚ã‚‹ã®ã‹ã€‚
 一家何人皆殺ã—ãªã‚“ã¦äº‹ä»¶ã¯å°‘ã—å‰ã¾ã§é »ç¹ã«ã‚ã£ãŸã®ã«ã€è¦‹äº‹ã«ã™ã¹ã¦å¿˜ã‚ŒåŽ»ã‚‰ã‚Œã€ã‚ã£ãã‚Šç„¡ããªã£ã¦ã—ã¾ã£ãŸã„ã¾ã«ãªã£ã¦ã“ã®æ‰‹ã®äº‹ä»¶ãŒè¨˜æ†¶ã‹ã‚‰åŽ»ã‚‰ãªããªã£ã¦æ²»å®‰ãŒæ‚ªåŒ–ã—ãŸã¨ã‹è€ƒãˆã‚‹ã®ã¯ãªã«ã‚†ãˆãªã®ã‹ã€‚ã»ã‚“ã¨ã¯ã™ã¹ã¦ã®çŠ¯ç½ªã‚’ã‚ã¤ã‹ã„ãŸã„ã®ã§ã™ãŒã€ã¨ã¦ã‚‚手ãŒå›žã‚Šã¾ã›ã‚“ã‹ã‚‰ã¨ã‚Šã‚ãˆãšå°‘年犯罪é™å®šã§ã‚„ã£ã¦ã„ã‚‹ã¨ã„ã†ã“ã¨ã§ã€‚
ã€€æƒ…å ±ã¨è¨˜æ†¶ã¨ã‚¦ã‚§ãƒ–を探る手ãŒã‹ã‚Šã«ãªã‚Œã°ã€‚失ã‚ã‚Œã¦ã—ã¾ã£ãŸè¨˜æ†¶ã‚’ã“ã†ã„ã†æ‰‹æ®µã«ã‚ˆã£ã¦å¤šãã®äººã€…ãŒå–り戻ã™ã“ã¨ã«ä»®ã«ãªã‚Œã°ã€ãã‚Œã¯ã‚¦ã‚§ãƒ–ãŒå¾“æ¥ã®ãƒ¡ãƒ‡ã‚£ã‚¢ã‚’凌駕ã—ã¦ä¸–ã®ä¸ã‚’å‹•ã‹ã—ãŸã¨ã„ã†æ˜Žç¢ºãªã²ã¨ã¤ã®é¡•ã‚Œã«ãªã‚ã†ã‹ã¨ã€‚å¤§çµ±é ˜é¸ã«å½±éŸ¿ã‚’ã‚ãŸãˆã‚‹ãªã‚“ã¦ã“ã¨ã‚ˆã‚Šã‚‚ã€ã“ã£ã¡ã®ã»ã†ãŒé¥ã‹ã«å¤§ãã„ã“ã¨ã ã¨ã‚ãŸã—ã¯è€ƒãˆã¦ã„ã¾ã™ã—ã€ãƒ¡ãƒ‡ã‚£ã‚¢ã®æœ¬è³ªã‚’示ã™ã“ã¨ã§ã‚ã‚‹ã¨æƒ³ã£ã¦ã„ã¾ã™ã€‚
 æ´å²ã®è»¢æ›ç‚¹ã‚’判りやã™ã„å½¢ã§ç¤ºã™ã«ã¯ã€ã‚„ã‚Šæ–¹ã¯ã„ã‚ã„ã‚ã‚ã‚‹ã¨æƒ³ã„ã¾ã™ãŒã€ãã®ã²ã¨ã¤ã¨ã—ã¦ã€‚ä¸èº«ã¯æ—§æ¥ã®ãƒ¡ãƒ‡ã‚£ã‚¢ã®ã‚‚ã®ã«éŽãŽãªã„ã¨ã„ã†ã®ãŒã€ãƒžã‚¯ãƒ«ãƒ¼ãƒãƒ³ã®ãƒ¡ãƒ‡ã‚£ã‚¢é€²åŒ–ç†è«–ã«å‰‡ã—ã¦ã„ã¦ãªã‹ãªã‹ã‚ˆã‚ã—ã„ã‹ã¨ã€‚
 ãªã‚“ã›ã“ã‚Œã ã‘ã®é‡ã‚’示ã™ã®ã¯æœ¬ã§ã‚‚æ–°èžã§ã‚‚テレビã§ã‚‚ä¸å¯èƒ½ã§ã™ã‹ã‚‰ã€‚昔ã®å°‘年犯罪ã«è©³ã—ã„æ–¹ãŒæ‹ り所ã«ã—ã¦ã„る『é’å°‘å¹´éžè¡Œãƒ»çŠ¯ç½ªå²è³‡æ–™ã€ã‚‚ã‚ã‚Œã ã‘分厚ãã¦ã‚‚é‡è¦äº‹ä»¶ã‚’ã»ã¨ã‚“ã©è½ã¨ã—ã¦ã„ã‚‹ã“ã¨ãŒã€ã“ã®ä½œæ¥ã‚’通ã˜ã¦ã¯ã£ãã‚Šã¨åˆ¤ã‚Šã¾ã—ãŸã€‚
 考ãˆã¦ã¿ã‚Œã°å°‘年犯罪データベースã¯ã¦ãªã«é™ã‚‰ãšã€ãƒ–ãƒã‚°ã¯å¾“æ¥ã®ãƒ¡ãƒ‡ã‚£ã‚¢ã‹ã‚‰ã®æƒ…å ±ã‚’å…ƒã«ã—ã¦ã„ã‚‹ã«éŽãŽãªã„ã¨ã„ã£ãŸè©±ã‚‚マクルーãƒãƒ³ç†è«–ã«å‰‡ã—ã¦ã„ã‚‹ã‚ã‘ã§ã€ã‚„ã¯ã‚Šæã‚‹ã¹ããŠã£ã•ã‚“ã§ã¯ã‚る。
 ãŸã ã—ã€æ¬¡ã€…ã¨æ–°ã—ã„æƒ…å ±ã‚’è¿½ã£ã‹ã‘ã¦ã„ãã ã‘ã¨ã„ã†<å½¢å¼>ã¾ã§ã‚‚ãŒæ—§æ¥ã®ãƒ¡ãƒ‡ã‚£ã‚¢ã¨åŒã˜ã§ã‚ã‚‹ã®ãªã‚‰ã€ãƒ¡ãƒ‡ã‚£ã‚¢é€²åŒ–ã¨ã¯äº‘ãˆãªã„ã‚ã‘ã§ã€‚
 データã¯å°‘ã—ã¥ã¤ç§»ã—ã¦ã„ã£ã¦ã€æœ€çµ‚çš„ã«ã¯80年分ã»ã©ãŒã‚¢ãƒƒãƒ—ã•ã‚Œã‚‹äºˆå®šã§ã™ãŒã€ã“ã‚Œã ã‘ã®åˆ†é‡ã‚’ã‚ã¤ã‹ã†ä¸–ç•Œã§åˆã‚ã¦ã®ãƒ–ãƒã‚°ã«ãªã‚‹ã‚ˆã†ãªæ°—ãŒã—ã¾ã™ãŒã€ã©ã†ã§ã—ょã†ã‹ã€‚ã™ã§ã«ä½•ç™¾å¹´åˆ†ã®æ´å²ã‚’綴ã£ãŸãƒ–ãƒã‚°ãªã‚“ã¦ã‚‚ã®ã‚‚ã‚ã‚‹ã®ã§ã—ょã†ã‹ã€‚
 考ãˆã¦ã¿ã‚Œã°ã€ã‚ãŸã—ã¯ãƒ–ãƒã‚°äº‹æƒ…ã«ã™ã“ã¶ã‚‹ç–Žã„。åŒã˜è¦æ¨¡ã®ã‚‚ã®ãŒä»–ã«ã‚ã‚‹ã®ãªã‚‰ãœã²æ•™ãˆã¦ãã ã•ã„。
 ã“ã‚Œã ã‘ã®åˆ†é‡ã«ãªã‚‹ã¨å¾“æ¥ã¨ã¯é•ã£ãŸè¦‹ã›æ–¹ã‚’ã—ãªã„ã¨ã©ã†ã—よã†ã‚‚ãªã„。ãªã‚“ã¨ã„ã†ã‹ã€ç«‹ä½“çš„ãªæ§‹ç¯‰ã§ãªã„ã¨ã€‚
 ã“ã‚Œã‹ã‚‰æ•°å¹´çµŒã£ã¦ã€å年以上ブãƒã‚°ã‚’続ã‘ã‚‹æ–¹ãŒå‡ºã¦ãã‚‹ã¨åŒã˜æ‚©ã¿ã‚’抱ãˆã‚‹ã“ã¨ã«ãªã‚‹ã®ã¨æƒ³ã„ã¾ã™ã€‚ã¤ã¾ã‚Šã€ã“ã®å°‘年犯罪データベースã¯ã¦ãªã‚’使ã£ã¦æ–°ã—ã„ウェブ形å¼ã‚’一足先ã«è¦‹å‡ºã—ã¦ãŠãã¨ã€æ¬¡ä»£ã®ã‚¦ã‚§ãƒ–ã¯ã‚ãªãŸã®ã‚‚ã®ã«ãªã‚Šã¾ã™ã€‚ãœã²ã“ã®ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿ã‚’使用ã—ã¦ã„ã‚ã„ã‚実験ã—ã¦ã„ãŸã ã‘ã‚Œã°ã€‚
 世ã®ä¸ã§ã¯æ–°ã—ã„å½¢å¼ã®æ¤œç´¢ã‚·ã‚¹ãƒ†ãƒ ã ã¨ã‹ã€ä¸‰æ¬¡å…ƒãƒ¦ãƒ¼ã‚¶ãƒ¼ã‚¤ãƒ³ã‚¿ãƒ¼ãƒ•ã‚§ã‚¤ã‚¹ã ã¨ã‹ã®è©¦ã¿ãŒç››ã‚“ã®ã‚ˆã†ã§ã™ãŒã€ã“ã†ã„ã†å…·ä½“çš„ãªã‚‚ã®ã®è§£æ±ºã‚’謀るã“ã¨ã«ã‚ˆã£ã¦æ§‹ç¯‰ã—ã¦ã„ãã»ã†ãŒç°¡å˜ã§ã‚ã‚‹ã‹ã¨å˜ã˜ã¾ã™ã€‚
 もã£ã¨ã‚‚ã€ä½•å¹´ã‚‚å‰ã®éŽåŽ»ãƒã‚°ã‚’èªã¿ç›´ã™ã»ã©ã®ä¾¡å€¤ã‚’æŒã£ãŸãƒ–ãƒã‚°ãŒã»ã‹ã«ã‚ã‚‹ã‹ã©ã†ã‹ã¯ã¯ãªã¯ã ç–‘å•ã§ã¯ã‚ã‚Šã¾ã™ãŒã€‚グーグルã‹ãªã‚“ã‹ã§å¼•ã£æŽ›ã‹ã£ã¦å¶ç„¶èªã‚€ãらã„ãŒã¡ã‚‡ã†ã©ã„ã„ã‹ã‚‚知れã¾ã›ã‚“。
 少年犯罪データベースã¯ã¦ãªã¯ã™ã¹ã¦èªã¿è¿”ã™ã ã‘ã®æƒ…å ±ä¾¡å€¤ãŒã‚ã‚‹ã¨æƒ³ã£ã¦ã¾ã™ã®ã§ã€ã‚‚ã†ã¡ã£ã¨æœ‰æ©Ÿçš„ãªæ§‹é€ ã«ã—ãŸã„。
 ã¨ã‚Šã‚ãˆãšã€ã„ã¾èªã‚“ã§ã„ã‚‹å¹´ã®ã‚¿ã‚¤ãƒˆãƒ«ãŒã‚µã‚¤ãƒ‰ã«ä¸¦ã¶ãらã„ã®ã“ã¨ã¯ã‚„ã‚ŠãŸã„ã§ã™ã€‚最新タイトルãªãžã€ã¾ã£ãŸãæ„味ãŒã‚ã‚Šã¾ã›ã‚“ã‹ã‚‰ã€‚ã‚ã¨éŽåŽ»ã®æ—¥ä»˜ã§ã‚‚æ–°ã—ãアップã•ã‚ŒãŸã‚‚ã®ã¯ã¾ã¨ã‚ã¦è¡¨ç¤ºã•ã‚Œã‚‹ã¨ã‹ã€‚
 プãƒã‚°ãƒ©ãƒŸãƒ³ã‚°ãªã©åˆ¤ã‚‰ã‚“ã‚ãŸã—ã«ã¯æ‰‹ã«è² ãˆã¾ã›ã‚“ã®ã§ã€ã©ãªãŸã‹ã‚ˆã‚ã—ããŠé¡˜ã„ã„ãŸã—ã¾ã™ã€‚
 ã»ã‚“ã¨ã¯ã‚ªãƒ¼ãƒ—ンソースコミュニティー的ãªã‚‚ã®ã§ã‚¸ãƒ£ã‚¹ãƒ©ãƒƒã‚¯ã®ä»£ã‚ã‚Šã‚’ã‚„ã£ã¦ã—ã¾ã†ã¨ã‹ã„ã†ã»ã†ãŒã€ã‚¦ã‚§ãƒ–ãŒå¾“æ¥ã®ãƒ¡ãƒ‡ã‚£ã‚¢ã‚’凌駕ã—ã¦ä¸–ã®ä¸ã‚’å‹•ã‹ã—ãŸã¨ã„ã†æ´å²ã®è»¢æ›ç‚¹ã‚’示ã™ã«ç›¸å¿œã—ã„ã“ã¨ãªã‚“ã§ã—ょã†ãŒã€ã‚ãŸã—ã¯ã‚ãŸã—ã®ã§ãã‚‹ã“ã¨ã‚’ã‚„ã‚‹ã—ã‹ãªã„ã—ã€ã¾ãŸæœ€åˆã‹ã‚‰ãã‚“ãªå®Œæˆåž‹ã¿ãŸã„ãªã“ã¨ã¯ç„¡ç†ã§ã¡ã‚‡ã£ã¨ã—ãŸã“ã¨ã‹ã‚‰ã¯ã˜ã‚ãªã‘ã‚Œã°ãªã‚‰ãªã„ã®ã‚‚ã€ã“れもã¾ãŸæ´å²ãŒç¤ºã—ã¦ã„ã‚‹ã“ã¨ã§ã‚ã‚Šã¾ã™ã€‚
 é¢å€’ã ã‹ã‚‰åŽŸæ–‡ã¯èªã‚“ã§ãªã„ã®ã ã‘ã©ã€ã“ã“ã«ã‚る日本語解説ã®éƒ¨åˆ†ã ã‘見るã¨ã€ãƒ†ã‚£ãƒ ・オライリーãŒã“ã‚Œã‹ã‚‰ã®ã‚ªãƒ¼ãƒ—ンソース・コミュニティã«æœŸå¾…ã™ã‚‹ã“ã¨ã¯ã€ä»¥å‰ã«ã‚ãŸã—ãŒ2003/7/26 <メディア循環>ã¯èµ·ã“ã£ã¦ã„ã‚‹ã®ã‹?ã«è¨˜ã—ãŸã‚ˆã†ãªã‚‚んらã—ã„。
 ã¾ã‚ã€ãã†ã ã‚ãªã€‚ãŸã¶ã‚“ã‚ãŸã—ãŒè˜ã‚‰ãªã„ã ã‘ã§ã“ã‚“ãªã“ã¨ã¯å‰ã‹ã‚‰äº‘ã£ã¦ãŸã‚“ã ã‚ã‘ã©ã€ã‚ã¡ã‚‰ã®å‹•ãを紹介ã™ã‚‹æ–¹ã€…ã¯ã“ã†ã„ã†éƒ¨åˆ†ã‚’ã—ã£ã‹ã‚Šæ—¥æœ¬èªžåŒ–ã—ã¦ãれんã¨æ¨ªæ–‡å—ã«å¼±ã„ã‚ãŸã—ãŒå›°ã‚‹ã€‚
 <メディア循環>ã¯ã€ã„よã„よã„ã¤èµ·ãã‚‹ã‹ã§ã¯ãªã誰ãŒèµ·ã“ã™ã‹ã®å•é¡Œã«ãªã£ã¦ããŸã¨ã„ã†ã“ã¨ã 。ã„ã‚„ã€å¤§ä¼æ¥ãŒèµ·ã“ã™ã®ãªã‚‰æœ¬è³ªçš„ãªå¾ªç’°ã«ã¯ãªã‚‰ã‚“ã¨äº‘ã£ãŸã»ã†ãŒã‚ˆã„ã‹ã€‚
 レッシグã®æ–°ã—ã„本ã§ã“ã‚“ãªã“ã¨ã¯è«–ã˜ã‚‰ã‚Œã¦ã„ã‚‹ã‚“ã ã‚ã†ã‹ã€‚æ‰ä¸¦å›³æ›¸é¤¨ã«ã¯ã„ã¾ã ã«å…¥ã‚‰ãªã„ã®ã§èªã‚“ã§ãªã„ã®ã ã‘ã©ã€‚ã‚‚ã†ã€ã¿ãªã•ã‚“飽ãã¦ã—ã¾ã£ã¦ãƒªã‚¯ã‚¨ã‚¹ãƒˆã‚‚出ã—ã¦ãŠã‚‰ã‚“ã®ã ã‚ã†ãªã€‚ã„ãらæ‰ä¸¦å›³æ›¸é¤¨ã®äºˆç®—ãŒæ¸›ã‚‰ã•ã‚ŒãŸã¨ã¯äº‘ãˆã€ã‚ã®æ‰‹ã®ã‹ã—ã“ãã†ã§æ–°ã—ãã†ãªæœ¬ã¯2人もリクエストを出ã›ã°å…¥ã‚‹ã§ã—ょã†ã‹ã‚‰ã€‚
 コンテンツã®è‡ªç”±ã®ç¢ºä¿ã‚’最優先ã•ã›ãªã‘ã‚Œã°ã„ã‘ãªã„ãªã©ã¨ã„ã†é¢¨æ½®ã‚’一時的ã«ã‚‚ã›ã‚ˆåºƒã‚ã¦ã€æµé€šçµŒè·¯ã€ã¤ã¾ã‚Šãƒ¡ãƒ‡ã‚£ã‚¢ã®è‡ªç”±ã®ç¢ºä¿ã®é‡è¦æ€§ã‹ã‚‰çœ¼ã‚’逸らã›ã¦ã„ãŸã®ã§ã€ã“ã‚Œã¯è‰¯ã„傾å‘ã§ã¯ã‚る。ã¾ã•ã—ãã€ã‚ã‚Œã“ãスーツã®æ‰‹å…ˆã ã£ãŸã€‚
 ソフトãŒã‚³ãƒ¢ãƒ‡ã‚£ãƒ†ã‚£åŒ–(ã©ã“ã§ã‚‚手ã«å…¥ã‚‹ã‚ã‚ŠããŸã‚Šã®æ—¥ç”¨å“化)ã—ã¦ã€ã‹ã¤ã¦ãƒãƒ¼ãƒ‰ã®ä¸–ç•Œã§ãƒ‡ãƒ«ç¤¾ãŒè‡ªåˆ†ã§ã¯ä½•ã‚‚作らãšã«ã©ã“ã§ã‚‚手ã«å…¥ã‚‹æœ‰ã‚Šç‰©ã®éƒ¨å“ã‚’è²·ã£ã¦ãã¦çµ„ã¿ç«‹ã¦ãŸã ã‘ã§æœ€å¼·ã®ãƒ‘ソコン会社ã«ãªã£ãŸã‚ˆã†ãªã“ã¨ãŒèµ·ã“ã‚Œã°ã€ãŸã—ã‹ã«ã‚ªãƒ¼ãƒ—ンソースã§ã‚½ãƒ•ãƒˆãªã‚“ã‹ä½œã£ã¦ã¦ã‚‚力ã¨è‡ªç”±ã¯ç¢ºä¿ã§ããªã„。メディアã®ã»ã†ã‚’抑ãˆãªã‘ã‚Œã°ã€‚
 グーグルã«ã™ã¹ã¦ã‚’æ¡ã‚‰ã‚ŒãŸã‚‰ã€ç™ºç”Ÿã™ã‚‹å•é¡Œã¯ã‚°ãƒ¼ã‚°ãƒ«å…«åˆ†ãªã‚“ã¦çš®ç›¸çš„ãªã“ã¨ã ã‘ã§ã¯æ¸ˆã¾ãªããªã£ã¦ãる。
 ã—ã‹ã—ã€è§£èª¬ã‚’èªã‚€é™ã‚Šã§ã¯ã€ã‚ªãƒ©ã‚¤ãƒªãƒ¼ã¯ãŠå‹é”帳や予定表を確ä¿ã—ã‚ã¨äº‘ã£ã¦ã„ã¦ã€ã“ã‚Œã¯ã¾ã‚巨大ä¼æ¥ã«è‡ªåˆ†ã®ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿ã‚’渡ã•ãªã„守りã®å§¿å‹¢ã¨ã—ã¦ã¯åˆ¤ã‚‹ã‘ã©ã€æ”»ã‚ã¦ã„ã£ã¦ã»ã‚“ã¨ã«ãƒ¡ãƒ‡ã‚£ã‚¢ã‚’抑ãˆã‚‹æ¦å™¨ã¨ã—ã¦ã¯ã—ょã¼éŽãŽã‚‹ã€‚コンピュータープãƒã‚°ãƒ©ãƒ ãŒã‚³ãƒ¢ãƒ‡ã‚£ãƒ†ã‚£åŒ–ã—ã¦ã€ãƒ¡ãƒ‡ã‚£ã‚¢ã‚’抑ãˆã‚‹ã¨ãªã‚‹ã¨ã€ã‚„ã¯ã‚Šã‚³ãƒ³ãƒ†ãƒ³ãƒ„ãŒé‡è¦ã«ãªã£ã¦ãる。レッシグもã“ã“ã¾ã§è¸ã¾ãˆãŸã†ãˆã§ã‚³ãƒ³ãƒ†ãƒ³ãƒ„ã®ã“ã¨ã‚’語ã£ã¦ã„ã‚Œã°è©•ä¾¡ã§ãã‚‹ã®ã ãŒã€‚
 ã‚ãŸã—ã¯ä¸€å¿œãã‚“ãªã¨ã“ã¾ã§è€ƒãˆã¦ã€ã‚ˆãã•ã‚“ã®ã¨ã“ã‚ã®ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿ä½œæˆã«æŽ›ã‹ã‚Šã£ãã‚Šã«ãªã£ã¦ã„ã‚‹ã®ã ã‘ã©ã€è€ƒãˆã¦ã¿ã‚Œã°çµ¶æœ›æ›¸åº—主人ã«ã—ã‹ã§ããªã„絶望書店ã®æ§‹ç¯‰ã‚’ã»ã£ãŸã‚‰ã‹ã—ã¦ã€èª°ã«ã§ã‚‚ã§ãã‚‹ã¯ãšã®ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿ä½œæˆã‚’ã‚„ã‚‹ã¨ã„ã†ã¯ãŠã‹ã—ãªè©±ã§ã€ã“ã‚Œã¯ãƒ¡ãƒ‡ã‚£ã‚¢ã®é‡è¦ãªè¦ç´ ã§ã‚るシステムé‹ç”¨ã®å•é¡Œã¨é–¢ã‚ã£ã¦ãる。ã†ã¾ã人をæ“ã‚Œã¦ã„ãªã„ã¨ã„ã†ã“ã¨ã§ã€‚
 オライリーã¯ã‚ªãƒ¼ãƒ—ンソース・コミュニティã«ã€Œã‚½ãƒ¼ã‚·ãƒ£ãƒ«ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ã€ã‚’P2Pã§ã‚„ã‚Œã¨äº‘ã£ã¦ã‚‹ã‘ã©ã€ã“ã‚Œã¯ã¤ã¾ã‚Šé‹ç”¨ã®å•é¡Œã¯ã†ã¾ã„å…·åˆã«ã‚¹ãƒ«ãƒ¼ã—ã‚ã¨ã„ã†ã“ã¨ãªã®ã‹ã€‚é‹ç”¨ãŒãªãã¦ãƒ¡ãƒ‡ã‚£ã‚¢ãŒæˆã‚Šç«‹ã¤ã®ã‹ã€‚メディアã¨ã¯ãƒãƒ¼ãƒ‰ã‚„ソフトã®ã‚ˆã†ã«ä½¿ã‚ã‚Œãªãã¦ã‚‚一応ãã“ã«å˜åœ¨ã™ã‚‹ç‰©ä½“ã§ã¯ãªãã€äººã€…ã‚’å‹•ã‹ã—ã¦ã“ãåˆã‚ã¦æˆç«‹ã™ã‚‹ã‚‚ã®ã§ã¯ã‚ã‚‹ã®ã ãŒã€‚
 利用者も身内ã°ã‹ã‚Šãªã‚‰ã€ãã‚Œã¯ãƒ¡ãƒ‡ã‚£ã‚¢ã§ã¯ãªãã¦å¤§ä¼æ¥ã‹ã‚‰é€ƒã‚Œã‚‹ãŸã‚ã®ã‚·ã‚§ãƒ«ã‚¿ãƒ¼ã«éŽãŽã‚“ãŒã€ãã‚“ãªã‚‚ã®ã‚’イメージã—ã¦ã„ã‚‹ã®ã ã‚ã†ã‹ã€‚
 iTunesミュージックストアãŒã§ãã‚‹å‰ã«æ—¢å˜ã®ãƒ¬ã‚³ãƒ¼ãƒ‰ä¼šç¤¾ã ã‘ã§ã¯ãªãオープンソース・コミュニティãªã‚“ã‹ã‚‚ã‚ã®æ‰‹ã®ã‚‚ã®ã‚’æˆç«‹ã•ã›ã‚‰ã‚Œãªã‹ã£ãŸã®ã¯ã€ã‚³ãƒ³ãƒ†ãƒ³ãƒ„ã®å•é¡Œã‚‚大ãã„ã‘ã©ã€é‹ç”¨ã®å•é¡Œã‚‚大ãã„ã¨æƒ³ã‚れる。
 ã„ã¾ã ã«iTMSã«æœŸå¾…を抱ã„ã¦ã„る輩ã°ã‹ã‚Šã ã—。既å˜ã®ãƒ¬ã‚³ãƒ¼ãƒ‰ä¼šç¤¾ã‚ˆã‚Šã‚‚ã†ã¾ãやる分ã ã‘ã‚„ã£ã‹ã„ãªå˜åœ¨ã«ãªã‚‹ã¯ãšã§ã€ä¸Šé™¸ã—ã¦ã„ãªã„日本ã¯ä»Šã“ãåƒè¼‰ä¸€é‡ã®ãƒãƒ£ãƒ³ã‚¹ã®ã¯ãšãªã®ã ãŒã€‚
 ã¨ã“ã‚ã§ã€1å¹´å‰ã«ã‚ªãƒ©ã‚¤ãƒªãƒ¼ãŒã‚½ãƒ•ãƒˆã®ã‚³ãƒ¢ãƒ‡ã‚£ãƒ†ã‚£åŒ–ã«ã¤ã„ã¦ã¶ã¡ã‚ã’ãŸæ™‚ã€ã‚¹ãƒ©ãƒƒã‚·ãƒ¥ãƒ‰ãƒƒãƒˆã§ã®ãã‚Œã«é–¢ã™ã‚‹è°è«–ã‚’èªã‚“ã ã‚“ã§ã™ã‘ã©ã€å°†æ¥çš„ãªã‚½ãƒ•ãƒˆã®ã‚³ãƒ¢ãƒ‡ã‚£ãƒ†ã‚£åŒ–ã¯ãŠã‚ã‹ã€ã™ã§ã«èµ·ã“ã£ãŸãƒãƒ¼ãƒ‰ã®ã‚³ãƒ¢ãƒ‡ã‚£ãƒ†ã‚£åŒ–ã«ã¤ã„ã¦ã•ãˆã¿ãªã•ã‚“本質をç†è§£ã—ã¦ã„ãªã„ã¿ãŸã„ã§ã³ã£ãã‚Šã—ã¾ã—ãŸã€‚ã“ã“ã¯ä¸€å¿œãƒ—ãƒã®ãƒ—ãƒã‚°ãƒ©ãƒžãƒ¼ã‚„オープンソース・コミュニティã«å±žã—ã¦ã„るよã†ãªæ–¹ã®ã„ã‚‹ã¨ã“ã‚ã ã¨æƒ³ã£ã¦ã„ãŸã®ã§ã™ãŒã€æ—¥æœ¬ã®ãƒ¬ãƒ™ãƒ«ã¨ã„ã†ã®ã¯ã“ã‚“ãªã‚‚ã‚“ãªã‚“ã§ã—ょã†ã‹ã€‚ã‚ãŸã—ãŒã‚¹ãƒ©ãƒƒã‚·ãƒ¥ãƒ‰ãƒƒãƒˆã‚’èªã‚“ã ã®ã¯ã“ã®æ™‚ã ã‘ãªã®ã§ã‚ˆã判らんã®ã§ã™ãŒã€‚
 åŒã˜é ƒã®2ã¡ã‚ƒã‚“ã®åŽ¨æˆ¿ãŒé›†ã¾ã‚‹ã‚ˆã†ãªæ¿ã§ã®è°è«–ã¯ã€ã•ã™ãŒã«ãƒãƒ¼ãƒ‰ã®ã‚³ãƒ¢ãƒ‡ã‚£ãƒ†ã‚£åŒ–ãらã„ã¯ãã¡ã‚“ã¨è¸ã¾ãˆã¦å±•é–‹ã•ã‚Œã¦ã„ãŸã®ã§ã™ãŒã€ã©ã†ãªã£ã¦ã„ã‚‹ã‚“ã§ã—ょã†ã‹ã€‚
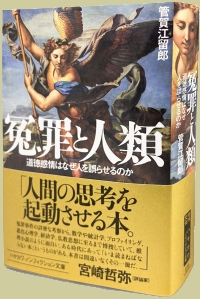
 絶望書店日記
絶望書店日記